- Germination Reactor
<私がベンチャーをつくった理由>リモートセンシング技術開発の知見を活かして新たな品種を生み出す(株式会社CULTA・野秋 収平さん)
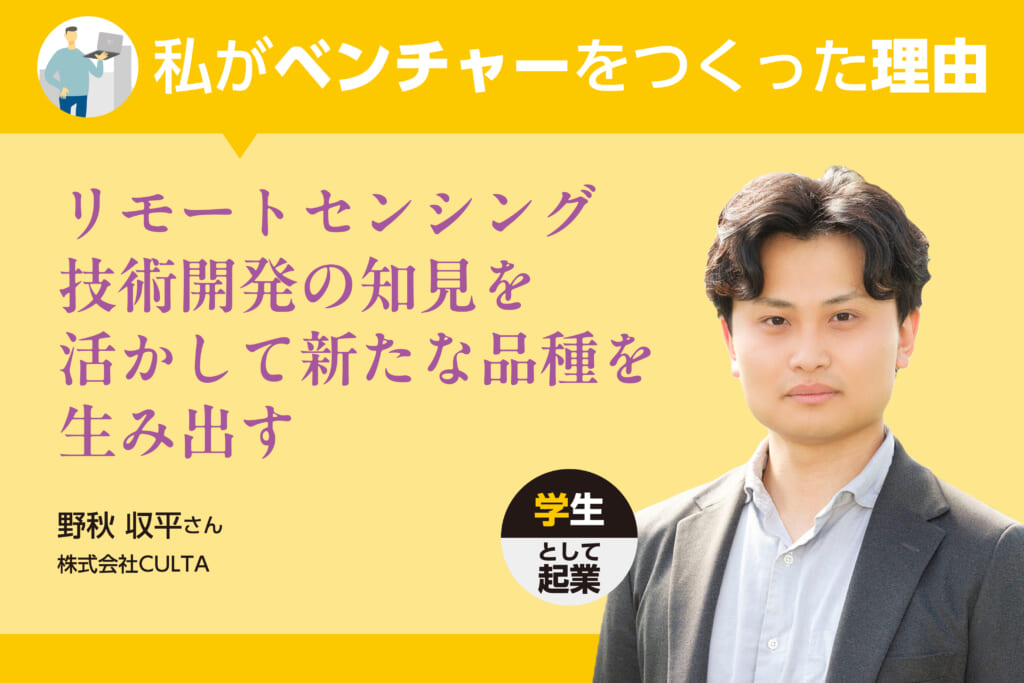
「世界中の農業の地位を上げ、強い産業に変える」をミッションに掲げ、株式会社CULTAで品種改良の高速化に取り組む野秋さん。大学院生の時に起業し農業に関わってきたが、学部の専門は化学工学だ。「本当に自分は農業に興味があるのか?」と疑問に思うこともあったという野秋さんは、どのように農業分野の研究開発に踏み出して行ったのだろうか。(incu・be 62号から転載)
自分が力を発揮できる場所はどこか?
野秋さんが農業に関わるようになったのは、高校からの関心の発露であったとも言えるが、その道のりは真っ直ぐな一本道というわけではなかった。祖父母が兼業農家をしており、農業は身近な存在だった。高校のときから農業や化学、環境に関心があり、大学のオープンキャンパスでは自然と農学部の展示へ足が向いていた。しかし、両親などとも進路相談する中で、農家に先はないかもしれないと感じたという。化学も好きでバイオマスエネルギーに関心があったため、これらが幅広く学べると考えて東京工業大学の工学部に進学した。しかし、バイオマスエネルギーのテーマでは研究予算が取れず、石油に関する研究をすることになったが、面白みは感じられなかった。
興味の真偽を確かめるために飛び込む
自分ならではの力が発揮できるような研究や技術はないものかと探していた学部3年の夏、たまたま見つけたのが、ITなどを掛け合わせて農業の効率化に取り組むスマート農業の新聞記事だった。もとより農業に関心があり、農業と工学の掛け合わせならライバルと差をつけることができて自分にあっているだろうという直感があった。しかし「この興味は本物なのか」という不安もあった。そこで農業系ベンチャーのインターンシップへ参加してみることにした。取り組んだのは、タイの農業ベンチャーの調査事業。学部とは違う農業分野の専門知識が必要だ。本を読む、勉強するといったことが苦手ですぐに飽きるという野秋さん。調査では、自分でも驚くほど勉強し、知識の蓄積ができたことから、「農業に対する自分の興味は本物だ」と確信したという。

▲人工環境を活用した高速品種改良の様子
異分野でも活きる、研究経験
「自分の意志で決めない決定は後悔する」と感 じた野秋さんは、農業への興味に従い、東京大学 大学院農学生命科学研究科に進学。農地のリモー トセンシング研究に取り組むと同時に、株式会社 CULTAを設立した。事業としてはじめに取り組 んだのは野菜や果物の流通販売だ。この時、ケー キ屋に卸していた「あまおう」のイチゴが他より も高値で取引され、ケーキも高く売られているこ とに気づいた。品種やブランドで差別化ができれ ば、作る側も売る側も利益をあげることができ る。ゴールデンキウイで有名なZespriなどの先 行事例もあり「この仕組みを作りたい」と思うよ うになった。 研究の中で、目標達成のために何が必要か構造 的に捉える能力が磨かれたという野秋さん。品種 改良という生物学的な研究領域でも怖気付くこと なく、研究者と議論しながら必要な技術を洗い出 し、仲間を集めることができたという。1人で始 めたCULTAには現在、ゲノム解析など品種改良 技術を専門とする仲間も加わり、もともと取り組 んでいた画像認識技術などと組み合わせて品種改 良の高速化をはかり、イチゴやサツマイモのオリ ジナル品種の開発にも取り組んでいる。
時代を創る品種を創りたい
野秋さんが現在考えているのは、次の100年 に必要な「時代を創る品種」の開発だ。大航海時 代の原動力となった胡椒、南北戦争のきっかけと なった紅茶など、人類の歴史を振り返ると時代を 動かしてきた作物がある。そして、その作物を生 み出す農業は、気候変動によって変化を強いられ る。農業分野は気候変動の影響を真っ先に受ける と言われ、実際に温暖化による果樹への高温被害 が発生している。そういう場面で高温にも耐える 品種の開発など、次世代に適応するような作物を 創り、広げていくことで持続可能な農業を実現で きないか。その地域、その時代に必要になる作物 は何か?先ずは現在のイチゴの品種改良を足がか りとして、そんな地球規模の課題に取り組んでい くことを構想中だ。野秋さんの、自分の興味関心 を確かめながら研究経験を活かして進んでいく姿 勢は、自分が挑戦する分野にたどり着くためのヒ ントになるかもしれない。
(文・戸上 純)
野秋 収平(のあき しゅうへい)プロフィール
1993年静岡県生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了。農業分野への画像解析技術の応用研究を行った。タイの農業スタートアップ、卸売市場等の業務経験を経て、2017年株式会社CULTA設立。高速育種技術を強みとし、品種開発から販売まで、農家の収益向上に資する「農業の垂直統合」を目指す。

