- Germination Reactor
<私がベンチャーをつくった理由>留年という挫折、そして「ビジョン」で繋がれる仲間との出会い(ファーメランタ株式会社・中川明さん)
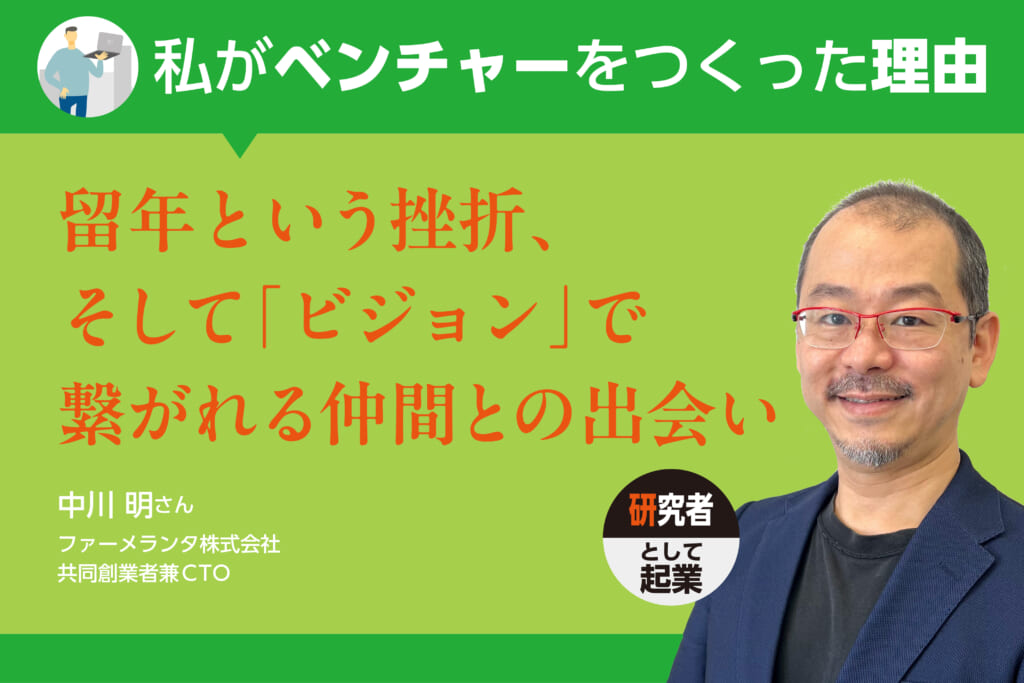
「理論上できることは、必ず実現できる」。バイオベンチャー企業ファーメランタ社の共同創業者・中川明さんは、「合成生物学による微生物発酵を通じて、有用物質生産手法に産業革命を」というビジョンを掲げ、2022年に会社を立ち上げた。生命の持つ潜在能力を最大化する製造方法の革命と、既存の概念にとらわれない理想の研究環境づくりが中川さんを突き動かすテーマだ。研究室での深夜の議論から、同じ志を持つ仲間となって、新たな挑戦が始まる。そんな研究者の軌跡を追った。(incu・be vol.67から転載)
挫折が導いた、やりたいことに向き合う決意
「自分は、3割の力で人並みの幸せな人生が送れると思っていました。頑張りたくなかったんです」。そんな中川さんの人生を大きく変えたのは留年という挫折だった。落ち込んでいたある時、パチンコ店で幸せそうに生きている人の姿を見て、本当に自分がやりたいことをやろうと思ったという。それが生命工学研究への道を開いた。
「3割の力とかは関係なく、初めて自分の意思で選び全力で向き合った道でした」と振り返る。博士課程修了後は企業の研究員として応用微生物の研究に携わった。そこでやりたい研究を思いついた。植物が多段階の反応プロセスを経て合成しているアルカロイド化合物。この有用成分を大腸菌を使って効率的に生産できたら面白いと思い、社内で提案するも却下されてしまう。
研究とビジョンを語り合った「お茶部屋」
その半年後、大腸菌でアルカロイド化合物の生産に成功したという論文が発表された。その著者が、後にファーメランタ社の共同創業者兼CSOとなる南博道さんだった。ちょうど南研究室でポスドクの募集があり、「絶対に南先生と研究したい」という気持ちで飛び込んだ。
「思い描いていた研究の方向性が南さんと完全に同じだったんです。ここなら理想の研究ができると確信しました」と中川さん。研究室のお茶部屋では連日、深夜まで熱い議論を交わした。しかし次第に、大学での研究に課題を感じるようになる。積み重ねた研究成果が、実用化という出口を見出せないまま論文で完結してしまう現実に直面していたのだ。この課題感について南さんと議論を重ねる中で、起業という選択肢が浮かんできた。そして、経営者の仲間との出会いを機に起業した。

「できるはずだ」を実現する物質生産
ファーメランタ社が取り組むのは、複数の生物から有用な遺伝子を探し出し、それらを最適な形で組み合わせる物質生産技術の確立だ。20種類以上もの遺伝子を1つの大腸菌の中に導入し、正常に働かせることに成功。まるで複数の生産ラインを持つ精巧な工場の様に、大腸菌の中に多段階の酵素反応を起こすことができる。
この技術の革新性は、生産効率を飛躍的に向上させる点にある。特定の植物に含まれ、鎮痛剤などに用いられる希少な有用成分を、植物を栽培することなく大腸菌で合成できるようになったのだ。さらに、各反応がスムーズに働くよう、遺伝子の働き方を緻密に制御する技術も確立した。これにより、1リットルの培養液からの生産量を、理論的な限界値となるグラム単位にまで引き上げることができた。「これからも研究者が『理論的には可能』と考えていることを形にしていきたい」と中川さんは語る。
個人の戦いから、チーム戦へ
中川さんの研究者としての意識は、起業を機に大きく変化した。論文を書くための研究に違和感を感じていた中川さんは、自分の考えに共感できる研究者は少なく、孤独な道を歩むしかないと思い込んでいた。
しかし、南さんと共に起業し、研究者を採用する立場になった。そこで独自の採用方法を取り入れた。採用試験では、ある論文を読み実用化までの道筋を提案するレポートが課される。解そのものの正しさよりも、レポートから見えるその人の研究に対する考え方や姿勢を重視しているのだ。
その結果、優秀な研究者が集まってきたことで、中川さんの考えは一変する。「こんなに研究が楽しいとは思わなかった。志を同じくする人たちと研究できる環境こそ、自分に必要だったのだと今は強く感じています」と中川さん。活発なディスカッションを通じて研究データも予想以上のペースで生まれ、新しい発見の連続だという。研究の実用化に向けて、中川さんは仲間の研究者と共に挑戦を続ける。
(文・高木史郎)
<プロフィール>
中川明(なかがわ・あきら)
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科博士課程修了。情報工学から生命科学分野へ転向し、生命を司るDNA情報に魅了される。協和発酵キリン株式会社博士研究員を経て、石川県立大学生物資源工学研究所応用微生物学研究室講師(現職)。2022年にファーメランタ株式会社を共同創業、CTOとして生命を工学的に制御する基盤技術の確立に取り組む。

