- Germination Reactor
<私がベンチャーをつくった理由>理論研究者の圧倒的な使命感に突き動かされた(TopoLogic株式会社・佐藤太紀さん)
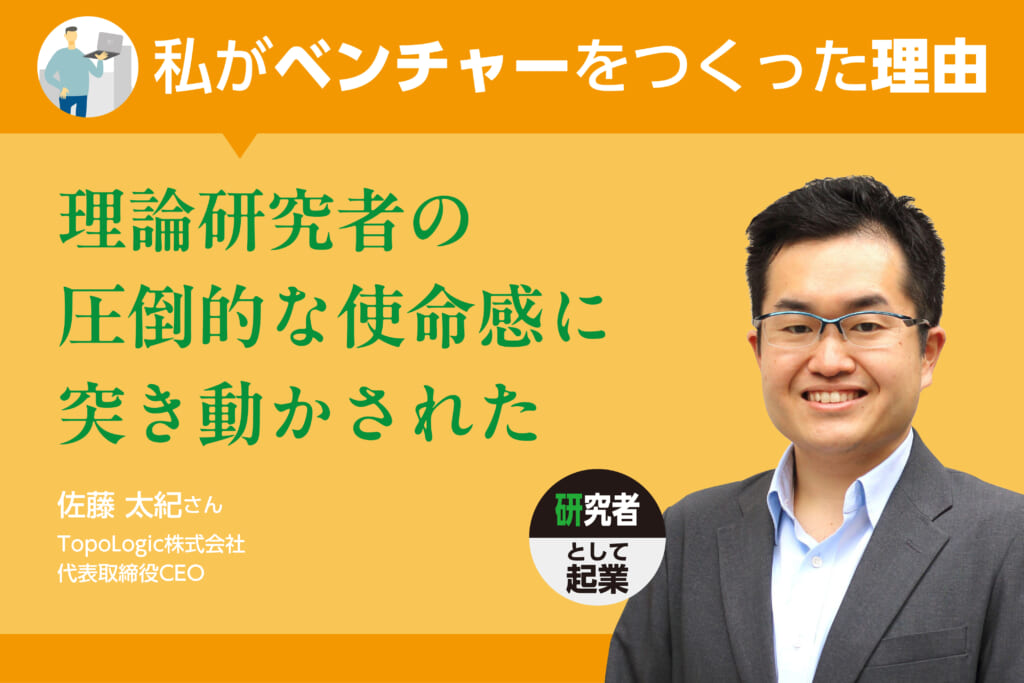
「チャレンジングな社会課題を解決し、豊かでサステナブルな世界を実現する」そんなビジョンを掲げ、2016年のノーベル賞でも話題になった新素材・トポロジカル物質の社会実装を目指すのがTopoLogic株式会社だ。代表取締役CEOを務める佐藤太紀さんが同社への参画を決意したのは、東京大学教授の中辻さんへの圧倒的な社会実装への使命感に感銘を受けたためだった。
もっと困難な、新技術の活用に挑戦したい
佐藤さんは学生時代、航空宇宙工学を専攻し、ガスタービンエンジンの高効率化を流体力学や熱力学を基に研究していた。航空宇宙工学は、流体力学や材料工学、制御工学、熱力学などの多様な工学分野を組み合わせ、応用先で必要な要求性能を満たすためのシステム工学的な考え方が強い学問である。「研究を通して、実際の応用に向けて技術を統合しながら開発を進める力や考え方が身についたのだと思います」と佐藤さんは話す。
卒業後は、製造業企業のクライアントを中心にマネジメントコンサルティングに従事し、その後産業用ドローンのスタートアップに参加するなど、製造現場を様々な視点から渡り歩いてきた。しかし、ドローン技術を通じて社会の課題解決を追求しつつも、もっと新しい技術の活用に挑戦したかったのだという。
決め手は、中辻さんの熱意への共感
そんな中、知り合いを通して中辻さんと出会う。トポロジカル物質は、量子的に特異な性質を持ち、既存の金属・半導体・絶縁体のいずれにも当てはまらない特殊な素材だ。内部が絶縁体でありながら表面は電気を通すという特性を持つものもあり、従来の素材では実現できなかった応用が期待されている。通常、この物質は低温・高圧という特殊な環境で機能することが多く、一般社会で活用することが難しかった。
そうした背景がありながら、常温・常圧下でも機能する素材を発見したのが中辻さんだ。「理学部物理学科の先生で理論研究を行いながらも、成果を社会実装しなければならないという使命感を強く持つ人です。こんな先生に出会ったのは初めてでした」と佐藤さんは話す。熱意を受け、自らもこの技術で世界を変えたいと強く考えるようになり、研究成果の応用を進めるべく中辻さんが立ち上げたTopoLogicへの参加を決意した。
トポロジカル物質に関しては全くの門外漢だった佐藤さんだが、航空宇宙工学で学んだ考え方を応用して会社の研究や経営について中辻さんと目指す先を議論している。現在はこの素材を活かし、熱流束センサや磁気メモリへの応用を目指している。特に熱流束センサは、温度が変化する前の熱の流入を観測することが可能で、この技術が実現すれば、従来の温度センサなどでは捉えられなかった機械内部の熱の動きを検出できるようになり、ものづくりにおける新たな可能性が開かれる。

異なる強みを持つからこそ仲間になれる
社会実装には、アカデミアと事業会社の文化の違いも課題になることがある。アカデミアでは、研究や理論の追求が重視され、応用された時の理想的なビジョンは提示されるが、その成果を世の中に広める方法が議論されることは少ない。
一方で、事業会社では実用性や市場のニーズに基づいた技術の開発が求められる。TopoLogicでは、これらの一見相反する考え方が融合されており、中辻さんが大きなビジョンを語りながら、それをどのように実装できるかを佐藤さんが考えるのだという。だからこそ、ただ技術を開発するのではなく、社会課題解決という大きな目的を持って活動できているのだろう。
「社会実装には障壁が多いですが、異なる専門性を持つ仲間の協力があれば必ず道は開けます」と佐藤さんは語る。この障壁を乗り越える力は、大学での研究活動を通じて得られたものだと振り返る。研究を通じて身につけた、問題解決能力やプロジェクト管理スキルは、実際のビジネス環境でも役立つのだ。今後も佐藤さんたちは、多彩な強みを持つ仲間を集いながら、社会実装に向かう旅を続けていく。
(文・滝野翔大)
<プロフィール>
佐藤太紀(さとう・たいき)
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻修士課程修了。6年間マッキンゼー・アンド・カンパニーにて製造業企業のクライアントを中心にマネジメントコンサルティングに従事。その後、産業用ドローンのスタートアップ企業にて大企業向けの共同開発や共同事業の構築を実行。2021年11月、当社代表取締役CEOに就任。経営コンサルティング及びスタートアップでの事業開発の経験を活かし、TopoLogic株式会社の事業の垂直立ち上げを目指す。

